「少子高齢化は行き着くところまで行くと、子供の数は増えてくる?!」地方にとって希望に満ちた法則になるかも!
昨日ブログに書いた、和歌山大学で行われた藻谷浩介先生の講演の続きです。一度聴いただけでは咀嚼が出来ないので、講演メモのマインドマッピングやスライドの写真、そして一緒に聞いていた主人と、あーでもない、こーでもないと、和歌山県からの帰りにずっと議論でした。
(写真中央が藻谷先生)
こんにちは。兵庫県北部・豊岡市で小さな宿&店の集客アドバイザー時々観光ガイドをしている今井ひろこです。当ブログへお越しいただき、ありがとうございます。
「少子高齢化」という言葉では見えてこないコトとは?
日本は総じて人口が減っていることはご存じのことと思います。2010年→2015年の間に大阪府でも人口は減少に転じました。近畿二府四県だと総人口で18万人減少しています。
中身を見てみると、特に0歳〜14歳(いわゆる子供)、15歳〜64歳(生産年齢人口)が減少がしているのですが、しかし。65歳以上は逆に増えていて、二桁%の伸びになっています。特に75歳以上を見ると大幅に増えています。子供が17万人減っているのに、老人は40万人も増えています。
これが首都圏だときっと人口増えているだろうから、首都圏のひとり勝ちだと思うでしょ?確かに首都圏の人口は、日本の殆どで人口が減っている中、唯一51万人増えているそうです。
が、しかし。その中身を見て私も驚きました。
実は中身を見ると65歳以上が2割程度増えていて、特に、75歳以上が24%の伸びと驚異的です。その一方、0−14歳の子供の数は待機児童問題などもあり、減少しています。また、15歳〜64歳の生産年齢人口も実際は減っているんですって。これは私も知りませんでした。そのため、ラッシュ時の列車は以前より込みようがマシになっているんだとか。
65歳以上が5年前に比べて76万人も増えているのですから、病院、老人ホームが足りず、家に閉じこもる、孤独死が日常茶飯事になっているのも納得です。
少子高齢化と言って、子供の数と年寄りの数だけ注目していたらアカン。大事なことは15歳〜64歳の生産年齢人口が減ってきている(=税収が下がる)ということをしっかり見なきゃ、と藻谷先生は仰っていました。
行き着くところまで行くと、子供の数は増えてくる?!
ところが、65歳以上の増加率が落ち着いている地域が出始めてきているそうです。例えば、島根県は全ての市町村で、他の地域よりも早くから65歳以上が減っている全国唯一の県だそうです。
65歳以上の増加スピードが行き着くところまで行くと、年配者の増加率が抑えらる一方、0〜14歳、15〜64歳の人口減少率が鈍化し、子供が増えてくる現象が見られる地域がでてきています。
例えば、和歌山県の飛び地・北山村は年配者が半数を占める地域ですが、早くから65歳以上が減っていますので、2010年→2015年も減っています。しかし、それを補うように若い移住者が少しずつ増え、子供の数は増えている年もあるそうです。
理由としては、年配者がしていた仕事(林業、農業、じゃばら)を、例えば年配者5人分の仕事を若い人が効率よく1人でこなすとしたら、一定の収入が得られるので、暮らせるようになります。子供を産み育てるということは、仕事や収入の見通しが無ければできませんので、その見通しが明るいと言うことを示していると思います。
また、年配者が減るということは福祉に回すお金が浮きますので、その分、移住者や子供の政策に予算を回すことが可能です。
つまり。
行き着くところまで行くと、子供の数は増えてくる?!
よって、その現象が早く起こりやすい
都市部より、地方のほうが心豊かに生き残るチャンスは高い
といえる、と藻谷先生は仰っていました。
(※但し、子供を産み育て易い、魅力的なまちになることが必須条件だけど)
どうして心豊かなのか、については、主人のブログで詳しく講演の中身を伝えていますのでそちらを参照下さい。
自分の住む自治体のデータも計算してみた…
ちなみに、上記の藻谷先生のデータと単純比較できないですが、国勢調査のデータで、兵庫県内で高齢化率上位を争う、私の住む香美町を見てみます。
| 人口 | 2010年 | 2015年 | 増減 | 増減率 |
| 0−14歳 | 2495人 | 2065人 | △430人 | △17% |
| 15−64歳 | 10680人 | 9374人 | △1306人 | △12% |
| 65歳以上 | 6521人 | 6630人 | +109人 | +2% |
| うち 75歳以上 |
3693人 | 3805人 | +112人 | +3% |
香美町の場合は、年配者の伸びは鈍化しつつも、0−14歳、15−64歳の減りが近畿二府四県の値よりも相当悪くなっています。想像は付いていたけど、見ると愕然とします。
65歳以上が加速度的に増える都市の多くは生産年齢人口、子供の数共に減り続け、少なくなる一方の税収を、増加する高齢者福祉へ回さねばならない。ということは、子供を産み育てる環境を整えることに予算を回せず、子供の数が減り続ける、という悪循環に。少々、高齢者福祉に回すお金を減らしてでも、20年後30年後を考えて、子供を産み育てる環境整備をした方が良いのでは・・・と聞いてて思いました。
都会からの移住政策も確かに必要。高卒で一旦但馬を出る人数と祝65歳になる人の数以上に抜けているなら、移住政策と並行して、15歳〜64歳の流出を抑える施策も考えておきたいですね。
☆★☆・・・☆★☆・・・☆★☆・・・☆★☆
地方の小さな宿と店の集客サポート
コムサポートオフィス 今井ひろこ
〒668-0022
兵庫県豊岡市小田井町5ー3フラッツオダイ201
TEL&FAX 0796−24−3139
「コムサポートオフィス」 で 検索!
Mail: info@@@imaihiroko.com (@は一つにして下さい)
URL:http://www.com-support-co.jp
★当社アドバイザーGAKUの骨太販促ブログ★
「コムサポートオフィスアドバイザー ガクの視点」
http://com-support-co.jp/blog
★SNSもお楽しみ下さい★
【今井ひろこ】
Facebook
https://www.facebook.com/hiroko.imai.matsumoto
Twitter
https://twitter.com/Imai_Hiroko
Instagram
https://www.instagram.com/imaihiroko/
【コムサポートオフィス】
【Facebookページ】セミナー案内等
https://www.facebook.com/コムサポートオフィス-298717267148682/
【Instagram】仕事風景、支援先でのひとコマなど
https://www.instagram.com/com_support_office/
<strong>★あなたにマッチするビジネスセミナーの予定は★
☆★☆・・・☆★☆・・・☆★☆・・・☆★☆
今井 ひろこ
最新記事 by 今井 ひろこ (全て見る)
- 第6期・南紀熊野観光塾「塾生講習」に参加して(5/n) 選ばれるだけの理由が無ければ売れない - 2019年1月17日
- 第6期・南紀熊野観光塾「塾生講習」に参加して(4/n) 着地型観光で選ばれる商品とは? - 2019年1月15日
- 第6期・南紀熊野観光塾「塾生講習」に参加して(3/n) ターゲットを一つに絞る - 2019年1月14日
関連記事
-


-
【登壇予告】京丹後市商工会主催セミナー「お客様アンケートの活用法」「Googleマイビジネス活用セミナー」の2回!
まだまだ残暑厳しい、豊岡からブログを書いています。連日35℃を超えますので、クー …
-


-
城崎で森山未來さんの「なむはむだはむ」を見て感じたこと
雪がちらちらと降る今日、城崎国際アートセンター(KIAC)へ初めてパフォーミング …
-


-
宿泊施設関係のビジネスカテゴリで民宿、ペンションを選びたいのに「無い!」と困っている方へ 〜Googleマイビジネス〜
今朝、スポットでコンサルティングをした宿泊施設さんから「登録でわからないことがあ …
-


-
2/17(土)山形県長井市で観光ガイド向けに地域づくりをテーマに講演を行いました
ここ2−3年は、ジオパークをなさっている地域だけでなく、新たに観光で地域づくりを …
-


-
名物オムライスに蔦屋書店、御金神社で福さいふと京都満喫!
先日、京都市内を半日観光し、懐かしかったり楽しかったりしたので、 ちょっとだけ報 …
-


-
佐津・訓谷集落から車で5分、柴山みなと前食堂凪(nagi)に行ってきた!
昨日、自宅から車で5分の所に出来た、ステキな食堂へ行ってきましたので、今日はその …
-


-
「理念」とは、思いを言葉で定義化してお客様を幸せにすること。 〜コムサポの理念を言語化してみた!〜
明日から3日間、怒濤のセミナー受講&開催Dayが続きます。明日は新入社員研修でプ …
-


-
豊岡市地域プロデューサー活動報告会聴講記〜あくまで私が感じたこと〜
今日は豊岡市の地域プロデューサーの活動報告会を途中から聴講してきました。 今日の …
-


-
被災していない私が取りたい行動☆熊本産を食べて被災地応援!
兵庫県北部の小さな宿と小売店の集客アドバイザー・今井ひろこ@コムサポートオフィス …
-


-
郵送料を安全に節約できる『クリックポスト』3つのメリット
先日、コムサポートオフィスで年4回出しているニュースレター「コムサポ通信」に付け …
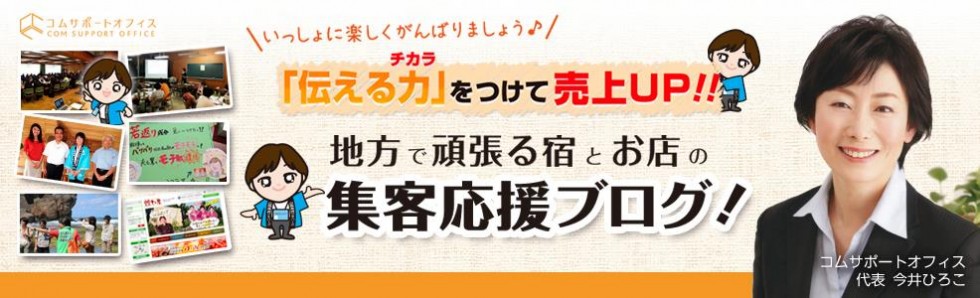






Comment
[…] 田舎で頑張る宿とお店の集客サポート「今井ひろこ… 「少子高齢化は行き着くところまで行くと、子供の数は増えてくる?!」地方にとって希望に満ちた法則になるかも! | 地 […]