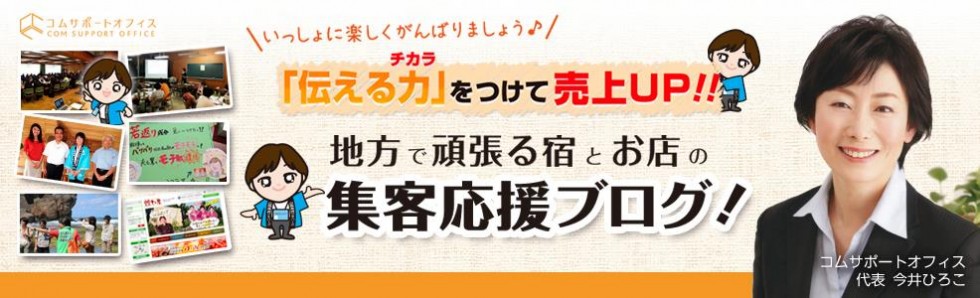地域づくり系の助成金申請書作成5つのコツ
2014/06/08
先日のプレゼン審査会の続きです。当日のプレゼンも大切なのですが、基本は申請書です。過去、NPOたじま海の学校では地域づくりやボランティア活動に助成金を何度も申請してきました。ただし、国レベルのン千万円モノでなく、数十万や数万のものです。今回、県民局の地域づくり活動助成申請では、他の活動団体の事業要約を見ることが出来まして、一部はプレゼンも聴くことができました。
その中で感じたことをコツとして5つ上げます。
- 各助成元の助成要件を踏まえた事業であること
今回申請した「夢シナリオ地域づくり活動応援事業」の場合、『①但馬夢シナリオ実現に向けて取り組む事業②夢但馬2014の趣旨を踏まえた事業③地域活性化に資する事業や、団体の創意工夫による地域の特性を生かした事業』とあります。そして、注目するのは次の項目【次の事業は対象外です】という項。
●営利を目的とする事業●宗教又は政治活動を目的とする事業●公序良俗に反する事業●大半を委託している事業●兵庫県から他の助成金を受けている事業
は誰でもわかりやすい箇所ですが、その他の
●既存事業●地区の定例行事等単に団体の構成員のみが利益を享受するような事業
を意外と見落とされている活動も見受けられました。サークル活動で会員だけが楽しむだけの事業や、相当にマニアックな事業についての活動は、他の地域への広がりや活動の広がりが限定的なため、評価が下がる傾向にあります。既存事業で毎年同じことを行っている団体の申請も見受けられました。私たちのNPO活動では毎年同じ「香美がたり」を申請しますが、新開拓するようなものを中心に事業内容を申請しています。そのようなチャレンジが必要です。 - 自己資金ゼロ円は避け、自己資金をねん出しましょう。
事業を行う上で絶対必要なのがヒトとカネです。特に事業資金の調達手段や調達先は審査の重要なポイントです。自己資金ゼロで申請を出したとき、もし助成申請額が減額した場合に事業がどこまで縮小するのかを、しっかりと記載する必要があります。お金が入ったらイベントや事業を行うが減額したら事業は行いません、と受け取られかねません。また、本気度が図れません。助成金申請というのは自己資金だけでは足りないから助けて下さいという申請ですから、ゼロ円からやって、通ったら事業を初めて行いましょう、ではないのです。収入ゼロで助成金のお金を使うだけ、イベントの周辺にお金が落ちない場合は、地域づくりとしては評価されないかもしれません。 - 成果物を作りましょう
これは民間会社の助成金のほうがむしろ言えるのですが、事業をしたときの成果物は作ったほうがいいです。「○○○○助成事業です」と民間の場合であれば宣伝ツールになるためです。また、形にして事業の成果を残すという意味からも必要です。勉強して楽しかったねーで終わり、となっては、振り返る術もありません。NPOたじま海の学校はガイド育成だけでなく、その養成講座で学んだことをガイド冊子にまとめ頒布して、事業資金も得るという「成果物」を毎回作ることにしています。 - 3年後、5年後のビジョンを申請書で示す
助成金を使う以上、単年度で終わるようなイベントや事業よりも、始動段階でのみ助成金を申請して事業を始め、2年目からはそれらを活用して事業資金を稼ぎ、3年目からさらに発展させることができるような事業に対して助成金を出します。例え、申請書では翌年度の事業予定だけを書く欄があったとしても、別の欄には5年後までのビジョンを書きましょう。審査する側の頭の中に明確に再現できるようであればポイント高いです。 - 申請の前に第三者や専門家の意見を聞く
申請事業の中には、事業内容に対する効果が果たして得られるのか?という疑問が審査委員から出た事業もありました。団体内で事業内容を吟味するだけでなく、専門家や第三者の意見を聞いて、事業内容をブラッシュアップすることも大切です。NPOたじま海の学校の場合は、協働相手となる大学の先生や観光協会さんなどにも事前に相談して、事業の中の細目についての優先順位を考えたり、根幹となるキーワードを決めたりしていました。
以上、私が地域づくり系の助成金申請書を書くときのコツをおおまかに5つお話しました。地域づくりは、その地域の人にHappyになってもらうことはもちろんのこと、但馬の各自治体が願う「交流人口の増加」を、地域づくり活動の際にも期待できる事業内容にする必要があります。もし申請を出すときに迷われたら、募集団体で相談会をする時がありますので、その場を活用するか、担当者に確認をしましょう。あるいは商工会や商工会議所、専門家に相談するのも手です。
中小企業、個人事業主の方、プレゼンの個人指導は
ミラサポで今井ひろこを活用!
今年度、国の支援制度で、年3回まで
指導料は一切不要。今がチャンス!
詳しくは私のこちらのブログを参照ください!


今井 ひろこ
最新記事 by 今井 ひろこ (全て見る)
- 第6期・南紀熊野観光塾「塾生講習」に参加して(5/n) 選ばれるだけの理由が無ければ売れない - 2019年1月17日
- 第6期・南紀熊野観光塾「塾生講習」に参加して(4/n) 着地型観光で選ばれる商品とは? - 2019年1月15日
- 第6期・南紀熊野観光塾「塾生講習」に参加して(3/n) ターゲットを一つに絞る - 2019年1月14日
関連記事
-


-
若い人たちの就業支援で、シカやイノシシから地域を守ろう
「ふるさと環境交流会in但馬」でのパネルディスカッションでは、会場からも深い意見 …
-


-
半円段ボール「えんたくん」でグループワークの効果絶大!
先日、養父(やぶ)市商工会女性部が主催して、但馬(兵庫県北部地方)の3市2町の女 …
-


-
松葉ガニと香住ガニと黄金ガニの食べ比べ講座を開催しました!(後編)
昨日の前編に続き、食事のお話です。今回のツアーで使われたカニのグレードが凄かった …
-


-
地域イベントには直近の為のものと未来に向けたものがある
昨日までのシカの関する環境問題、いかがだったでしょうか。多くの地方において無関心 …
-


-
田舎で出る杭を打たれないようにする方法
少し前になってしまいましたが、今年も70名以上の人が集まり、ジオパーク&但馬大交 …
-


-
真の「宿のおもてなし」を感じた旅館・宝生亭<3・終>仲居のめぐみさんの巻
昨日からご紹介している、主人のお友達の旅館、石川県山代温泉「宝生亭」の驚異のリピ …
-


-
SNSの登場で宿の看板は「思い出して頂く」最強アイテムに。〜宿泊施設の持続化補助金申請〜
昨日、4000文字近いジオパークのブログを書いたので、今日は柔らかめの宿販促ブロ …
-


-
小規模事業者のみなさま、商工会をもっと活用しましょう!
中小企業庁の中小企業&個人事業主の商売をサポートする「未来サポート事業」(通称: …
-


-
人口減少の中、交流人口を増やしたほうがいい理由
先週3日と4日に行われたじゃらんリサーチセンター主催の観光セミナーに参加して、計 …
-


-
じゃらんリサーチセンター主催の「観光振興セミナー」に参加してきました
今日は日帰り強行軍で大阪までリクルートライフスタイル「じゃらんリサーチセンター」 …